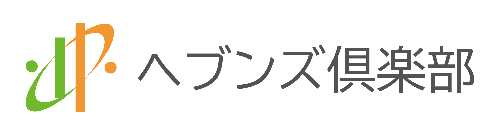.jpg)
忘年会の起源を深掘り!いつから始まった?日本ならではの伝統行事?
年末が近づくと、会社や友人、サークル仲間と「忘年会」の計画を立てるのが日本の恒例行事ですよね。美味しい食事やお酒を囲み、一年の労をねぎらうこの習慣は、いつから、どのようにして始まったのでしょうか?今回は、忘年会の知られざる起源とその歴史について深掘りしてみましょう。
「年忘れ」は鎌倉時代から? 武士が始めた厄払い
忘年会の直接的な起源をたどると、諸説ありますが、最も有力なのは鎌倉時代に武士の間で行われていた「年忘れ」という集まりだと言われています。
戦に明け暮れる日々を送っていた当時の武士たちにとって、年末は一年間の苦労や、もしかしたら戦場で命を落とすことになったかもしれない嫌な出来事を「忘れる」ための大切な区切りでした。彼らは酒宴を催し、その年の嫌なことや厄を清算し、新しい年を清々しい気持ちで迎えようとしたのです。これは単なる飲み会というよりも、心機一転を図るための儀式的な意味合いが強かったと考えられています。
室町時代の雅な「連歌の会」もルーツの一つ
もう一つの起源として挙げられるのが、室町時代に貴族や文化人の間で流行した「連歌(れんが)」の会です。連歌とは、複数の人が上の句と下の句を交互に詠み継いでいく和歌の一種で、知的ゲームのようなものでした。
年末に開かれる連歌の会は「年忘れの連歌」と呼ばれ、句を詠むだけでなく、酒食を伴う宴会としても大いに楽しまれていました。当時の記録には、こうした宴の様子が描写されており、現代の忘年会に通じる「一年の終わりを共に祝う」という要素が見られます。雅な貴族文化が、後の忘年会に影響を与えたのかもしれません。
江戸時代に庶民へと広がり、現在の形へ
鎌倉時代の武士や室町時代の貴族の習慣だった「年忘れ」が、広く庶民の間に浸透し、現在の「忘年会」に近い形として定着したのは江戸時代です。
この時代になると、経済活動が活発になり、商売人や職人、そして町の人々の間でも年末に集まって一年間の労をねぎらう習慣が広がっていきました。商家では、お得意様への感謝を込めて宴を開いたり、従業員の慰労のために宴席を設けたりするようになります。また、友人や趣味の仲間同士で集まって酒を酌み交わし、一年の出来事を語り合うことも一般的になりました。
この頃には、単に厄を払うだけでなく、人間関係の円滑化や親睦を深めるという、現代の忘年会が持つ重要な側面が強く意識されるようになったと考えられます。年末に賑やかに集まって飲食を共にするというスタイルが、この江戸時代に確立されたと言えるでしょう。
現代の忘年会:変わらない「区切り」の重要性
時代を経て、忘年会は「忘れる」という字が表すように、一年間の苦労や嫌な出来事を水に流し、新たな気持ちで新年を迎えるための大切な区切りとして、日本の文化に深く根付いています。
コロナ禍を経て、働き方や人との交流の仕方が多様化する中で、忘年会のあり方も少しずつ変化しているかもしれません。しかし、仲間と共に一年を振り返り、労をねぎらい、未来への希望を語り合うという本質的な価値は、これからも変わることなく受け継がれていくことでしょう。
今年の忘年会は、その深い歴史に思いを馳せながら、より一層楽しんでみてはいかがでしょうか。
【穴場】長野市で忘年会ができる穴場
結婚式場テラスグランツ
長野県長野市南長野妻科88
026-234-4122
・10名様以上のご予約で、マイクロバスの無料送迎あり(長野市内限定)
・忘新年会プランの詳細はお電話で
・施設の情報は以下のリンクより